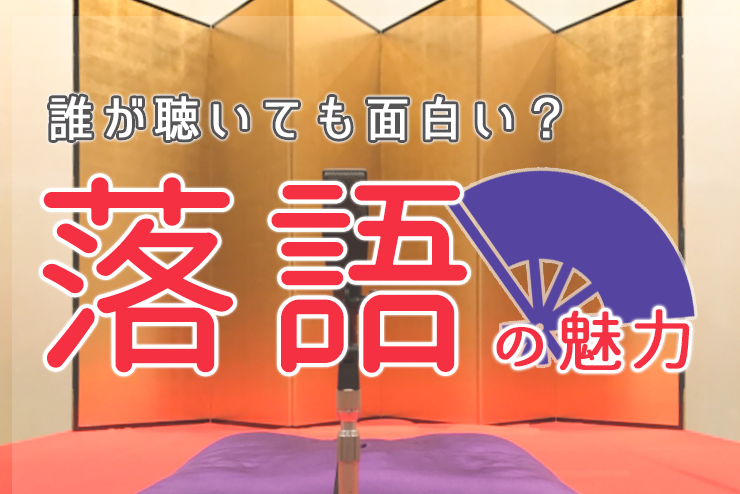
これまでに落語を見に行ったことがあるでしょうか?「敷居が高そう」「内容が分からないのでなんだか退屈そう」などの理由から、見に行ったことの無い人も多いかもしれませんね。
しかし、それでは勿体ない。実は落語は思っているほど難しくないのです。
落語は今や世界中から注目されている日本の伝統芸能です。日本の文化をしっかり分かっていないと理解できないのでは?海外の方に面白さは伝わりにくいのでは?と疑問に思ってしまいそうです。
落語は耳だけでなく目でも楽しむ芸術です。 滑稽な話や人間臭い失敗談、人情に訴えかけるような話を演者が身振り手振りをしながら話し進めていきます。
難しい表現で笑いを誘うものではなく、あくまで誰にでも分かりやすい面白さが魅力と言えるでしょう。そのため、日本人の根強いファンが居るのはもちろん、海外でも人気が高まってきているというわけなのです。
落語の基本について知り、ぜひ関心を持っていただけたら嬉しいです。
落語とは
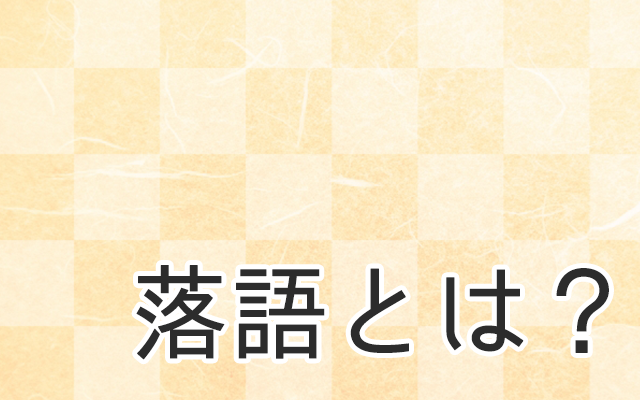
そもそも、落語とは一体どういうものなのか。改めて聞かれると答えるのに困ってしまうかもしれません。落語の基本について学んでいきましょう。
落語の特徴
落語は歌舞伎や能など他の伝統芸能と違い、 一人で何役もの登場人物を演じます。 扇子と手ぬぐいの他は何も持たず、身振りと手振り、そして話し方や声色だけで役柄を演じ分けます。
衣装や舞台装置なども極力使わず、演者の技巧と聴き手の想像力で噺の世界を広げていくのが特徴。噺が上手な落語家になると、目の前にその噺の映像がありありと浮かんでくるよう。
大掛かりなことは何もない、とてもシンプルで身近な芸能です。それだけに落語家の技量が大きく影響を与える、どこまでも奥が深い伝統芸能なのです。
落語は噺(はなし)と呼ばれることもあります。落語の演目で話される物語のことを噺と呼ぶことも。
また、落語家のことは噺家(はなしか)ともいいます。
落語の「オチ」
落語の噺には最後にオチがつくのが特徴です。 オチは「下げ(サゲ)」とも呼ばれます。
このオチとは、噺の最後にある気のきいた結末 のこと。
考えオチ、廻りオチ、間抜けオチ、しぐさオチなど・・。オチの種類は数多くあります。この噺のオチはどれだろうと考え込んでしまうのではなく、どう落ちるのかを楽しむことが大事です。
そもそも、落語という名前は落とし噺と呼ばれていたことからその名前が付きました。
噺はさまざま
噺の種類は数多くあります。笑い話だけでなく、人情噺や旅の噺。町人が主役の噺、武士が主役の噺、与太郎噺、酒飲みの噺など この他にもたくさん。自分の好きな噺を探してみるのも面白いですよ。
また、好きな噺が見つかったらぜひ色々な噺家のものを聴いてみましょう。それぞれ個性が出て更に魅力を感じるはずです。

落語の噺に数多く登場する与太郎(よたろう)。これは特定の人物ではなく、落語に登場する架空の人物です。間抜けな失敗ばかりする人物として話されることが多く「バカ」「役立たず」などの代名詞として呼ばれることも。
しかし、その人間くさい間抜けさは笑いを誘うのに一役も二役も買っていると言えるでしょう。
与太郎の他にも「熊さん」や「八っぁん」という架空の人物もよく噺に登場します。
落語の歴史
落語の始まりは室町時代末期から安土桃山時代にかけ、戦国大名のそばに仕えて話の相手をしたり、世情を伝えたりする「御伽衆(おとぎしゅう)」と呼ばれる人たちからでした。
その御伽衆の一人、安楽庵策伝(あんらくあんさくでん)という浄土宗の僧侶は、オチのつく噺を披露してたいへん喜ばれました。 その安楽庵策伝が説教の題材としてメモしておいた話を集めたのが醒睡笑(せいすいしょう)です。
醒睡笑は現在も話されている落語の元になった話も多く収載されいるなど、落語に大きな影響を与えています。
このことから安楽庵策伝は落語の祖と言われることもあります。
生で落語を観るなら
落語に興味が出てきたでしょうか?少しでも面白そうと感じたのであればぜひ落語を観に行ってみましょう。
落語は寄席と呼ばれる会場で行われています。寄せではほぼ毎日公演が行われており「昼の部」「夜の部」に分かれています。
基本的には入れ替え制ではないので「今日は落語の世界に浸るぞ」というときには一日中落語を楽しむことが出来る場所です。
寄席について
寄席では落語だけを延々と観るのではありません。落語の他にも漫才、漫談から手品、曲芸まで。実にバラエティー豊かな演目が行われており、観客を飽きさせることがありません。
前座の落語の後、漫才や手品などの演芸と二ツ目の落語。そして最後に登場するのが真打ちです。どの演目もテンポよく進んでいくので、あっという間に時間が過ぎていきます。
寄席には前売り券や席の予約などは無い場合が多いです。前もっての準備は特に必要ないので「時間が空いたから寄席に行こう」という気軽さで行くことができます。
また、きちんとした格好でないといけないというわけではもちろんありません。普段の洋服のままで大丈夫です。しかし、寄席に行くために着物を着るというのも素敵なことかと思います。挑戦してみたい方はぜひ着物で寄席に行ってみてください。

日本各地で行われる落語会
近所に寄席が無い。遠くまではなかなか足を運べないという方にオススメなのは落語会です。
落語会は日本各地で行われているもので、タイミングが良ければ近所のホールなどで落語を楽しむことが出来るかもしれません。大規模なものから小規模なものまで、各地で様々なテーマの落語会が開催されています。
ぜひ近所のホールなどの公演状況などを調べてみてくださいね。
