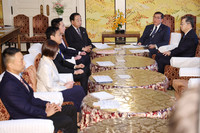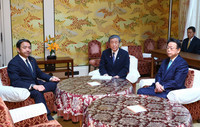ライドシェア、全国に拡大=タクシー不足対応、開始から1年

一般のドライバーが自家用車を使って有償で乗客を運ぶ「日本版ライドシェア」の開始から8日で1年となる。これまでに全都道府県で導入が決定。タクシーの不足を補う新たな移動手段として、住民や観光客の利用が広がりつつある。
ライドシェアは昨年4月、タクシー会社が運行管理を担うことを条件に、東京都内や京都市などの大都市部で開始。その後、全国に広がった。
国土交通省によると、大都市部ではライドシェアの導入後、アプリで配車依頼に対応できた割合が改善。タクシーだけでは7割程度だった早朝や深夜の時間帯では9割以上となった。東京23区などでは、これまでに約3300人がドライバーに登録した。
コロナ禍を経てタクシー台数が激減し、飲食店が打撃を受けたという群馬県桐生市は昨年11月に導入。LINEで簡単に配車できる仕組みを地元企業が構築し、夜間には最大5台が稼働する。市の担当者は「日常的な公共交通機関では賄えない時間帯に役立っている」と話す。
山形県尾花沢市では昨年12月、温泉街に向かう観光客らの足を確保するため、ライドシェアの運行を開始。冬場に仕事が少ないというスイカ農家などが運転を担う。大阪・関西万博が開かれる大阪では規制緩和が進み、今年2月から大阪市などで毎日24時間体制で稼働中だ。
国交省はライドシェアの運行主体をバスや鉄道事業者にも広げる方向で、近く実証事業に乗り出す。バスやタクシーを利用できない「交通空白」の解消に向け、普及を後押しする。
【時事通信社】
〔写真説明〕ライドシェアに使用される車両=3月31日、群馬県桐生市
2025年04月05日 13時31分