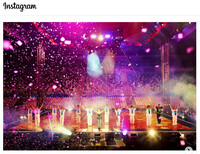密林にスマトラ横断鉄道の軌跡=案内板に「ロウムシャ」の字―駅舎、機関車など現存・インドネシア

第2次世界大戦末期、インドネシア西部のスマトラ島に旧日本軍が石炭や物資輸送のために敷設した「スマトラ横断鉄道」。現地人や捕虜らが建設に従事させられ、大勢の死者を出したが、タイ・ビルマ間の「泰緬鉄道」と比べ、その存在はほとんど知られていない。戦後80年がたち線路は見当たらないものの、今でも密林の中に一部残された駅舎や機関車などが、当時の面影を現代に伝えている。
西スマトラ州の州都パダンから車で約4時間。山間部のジャングルの細い道を擦り抜けて進むと、住宅街の中に駅舎が現れた。とは言っても駅であったことを示すのは「ムアロ」という看板だけ。建物は民家の倉庫として使われており、指摘されなければ気付かないが、近所の子どもたちに尋ねると「駅だったんだよ」と元気な声が返ってきた。
パダンからムアロまでは既に旧宗主国のオランダが敷設した鉄道があった。スマトラ横断鉄道はムアロ駅を起点とし、東隣のリアウ州の州都プカンバルまでの約220キロをつないだ。地形は険しく、今でも車で10時間はかかる。完成したのは、くしくも昭和天皇が「玉音放送」で国民に敗戦を伝えた1945年8月15日のことだった。
横断鉄道の建設開始は、戦局が急速に厳しさを増した44年1月。制海権、制空権を失った中で物資輸送路としての役割のほか、ムアロ近くの炭鉱から隣のマレー半島に製鉄のための石炭を運び出す目的があったとされる。終点プカンバルからは船でマラッカ海峡に下ることができた。
ムアロ駅近くの村には、当時の機関車が簡易な屋根の下で保存されている。さびて朽ちかけているものの原形はとどめている。案内板には、オランダ統治下にドイツの工場から持ち込まれたとあるが、近所の男性は「横断鉄道では使われることはなかった」と話した。
インドネシア語の紹介文の中で最も目を引くのは、「ロウムシャ(労務者)」という言葉だ。10万人以上のインドネシア人が安価な労働力として動員された際に使われ、広がった。地元女性記者は「小学校の歴史の授業で必ず習うので、みんな知っている」と明かす。
プカンバルの街中には、作業中に命を落とした労務者の霊をなぐさめる石碑も建てられている。碑文には日本に労働を強いられた同胞に寄り添う言葉が記されていた。(プカンバル=インドネシア=時事)。
【時事通信社】
〔写真説明〕オランダ統治時代にドイツの工場から持ち込まれた機関車=4日、インドネシア西スマトラ州
〔写真説明〕「スマトラ横断鉄道」の建設に動員され、亡くなった多くのインドネシア人の霊をなぐさめる石碑=5日、インドネシア・リアウ州プカンバル
〔写真説明〕「スマトラ横断鉄道」の起点となったムアロ駅の駅舎。現在は民家の倉庫として使われている=4日、インドネシア西スマトラ州
2025年08月14日 07時10分