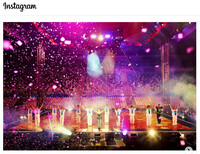対米同盟、戦後日本外交の柱

【ワシントン時事】日本は1952年のサンフランシスコ講和条約と旧日米安全保障条約の同時発効を経て、対米同盟を柱に戦後国際社会に復帰した。トランプ政権下の米国で同盟に厳しい視線が注がれる中、ジョンズ・ホプキンス大ライシャワー東アジア研究所のケント・カルダー所長と外交問題評議会のシーラ・スミス上級研究員に、日本の歩みと日米同盟の展望を尋ねた。
◇日米、「盾と矛」に変化―K・カルダー氏
―日米は戦後、同盟を結び発展させてきたが、重要な節目は。
1960年の日米安全保障条約改定は(内乱条項の削除など)植民地主義的な色彩を軽減した。中曽根康弘、小泉純一郎、安倍晋三の3人の首相は、長期政権の中で同盟を著しく強化した。ハト派である宏池会出身の岸田文雄前首相が、防衛予算の対国内総生産(GDP)比2%への引き上げや(反撃能力保有を明記した)安保3文書を作成したことも重要だ。
―トランプ大統領は同盟の「片務性」に不満を示している。
日本が同盟に「ただ乗り」しているという議論は誇張がある。在日米軍駐留経費の日本側負担(思いやり予算)は高額で、他の同盟国より負担が大きい。これまでは(日本は盾、米国は矛と)役割が違ったが、集団的自衛権の行使容認が法制化され、時代は変わった。今後ますます相互補完的な関係になるだろう。台湾海峡の安定維持は日米の大きな課題だ。
―米側には防衛費を対GDP比5%に引き上げるよう求める声もある。
中国の急速な軍拡は世界の安全保障構造にとって脅威だ。主要国は国防費を拡大する必要がある。ただ、5%かどうかは議論がある。トランプ政権の要求には極端なものもある。重要なのは金額より方向性だろう。
同盟強化は軍事重視で進んだが、今後視野を広げる必要がある。半導体をはじめとする重要技術協力、気候変動対策などだ。日本は軍民両用技術に長け、製造業の基盤を持つ。光ファイバーケーブルなどの海底通信インフラ(保護)、重要鉱物の海底採掘、海運・造船など海洋分野で協力の裾野を広げるべきだ。
経済面でも共通利益がある。エネルギーや食料で、米国は潜在的な供給国だ。14億の人口を抱える中国にはいずれも弱みになる。
―トランプ氏の高関税政策により、日米関係が揺らぐ懸念は。
トランプ氏はディール(取引)外交を好むが、思慮深く戦略的な側面も持つ。(日米貿易摩擦が激化した)80年代から考え方が変わっていないとすれば、日本の重要性を理解し、最良のディールを目指すだろう。
◇巧みに戦後乗り切る―S・スミス氏
―日本の戦後80年の歩みをどう評価するか。
日本は世界的には、国際通貨基金(IMF)などのブレトンウッズ体制に参加してその維持に貢献し、国連平和維持活動(PKO)をはじめ国連の各種活動を支持してきた。地域でも東南アジア諸国連合(ASEAN)地域フォーラム(ARF)などを推進した。
積極的な外交的役割を果たし、米国との同盟を通じ自国の安全を確保してきた。これらすべてが、外国との直接衝突を避ける上で役立った。日本は戦後を極めて巧みに乗り切ってきた。
―吉田茂元首相が基礎を築いた軽武装・経済重視路線、いわゆる吉田ドクトリンが重要だったのでは。
米日同盟という基盤、経済復興、限定的な独自の軍事力、この三つが日本を支えてきた。当初吉田ドクトリンが80年間続くとは誰も考えなかったが、世界的な制度的枠組み、冷戦後に日本が地域で構築を助けた制度的枠組みがあったからこそ、吉田ドクトリンは今日まで続いてきた。
―戦後の日本における日米同盟の重要性は。
同盟が全てというわけではないが、基盤であることは間違いない。とりわけ「核の傘」の重要性は高まり続けるだろう。
―同盟の実効性に懸念を抱いているか。
米国は80年の間に戦略的縮小期を経験してきた。朝鮮戦争後、ベトナム戦争後など、米国が「全ての国の防衛に関与する必要はない。同盟国はもっと自分たちで力を尽くすべきだ」と語った時があった。誰もがトランプ大統領ばかりを話題にするが、間違いだ。
ただ、もう一つ別の要素がある。日本に対する安全保障上の脅威がかつてないほど大幅に増していることだ。脅威が高まる一方で、米政府は同盟に強い疑義を呈しており、これらは同時に起きている。同盟史上、例のないことだ。
―同盟の行方に楽観的か、悲観的か。
中国に対抗する上で、米国民が日本は必要ではないと考える状況は想像できない。両国の利害関係が根本的に変わったとは思っていない。
【時事通信社】
〔写真説明〕インタビューに答える米ジョンズ・ホプキンス大ライシャワー東アジア研究所のケント・カルダー所長=7月18日、ワシントン
〔写真説明〕シーラ・スミス
米シンクタンク外交問題評議会上級研究員(外交問題評議会提供・時事)
2025年08月14日 12時39分