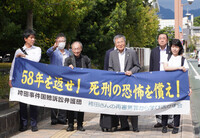共同研究者「大変うれしく誇り」=制御性T細胞の鍵特定―坂口さんノーベル賞で

ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大の坂口志文特任教授とともに、過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」の仕組みを解明した東京大の堀昌平教授(免疫学)が、11日までに時事通信の取材に応じた。坂口研究室に2003年まで2年間在籍した堀教授は「大変うれしく誇りに思う」とした上で、「厳しくも温かく研究者を育てる方で、自分の観察を信じて考え抜く姿勢を学んだ」と振り返った。
堀教授によると、1990年代までは免疫反応をどう活性化させるかが研究の主流で、抑制的に働く細胞の存在には否定的な見方が強かった。しかし、坂口さんが95年、たんぱく質「CD25」が制御性T細胞のマーカー(目印)になるとの論文を発表すると、流れが変わった。
さらに、堀教授や坂口さんらが中心となって制御性T細胞をつくる上で重要な遺伝子「FOXP3」を特定。通常のT細胞にこの遺伝子を加えることでブレーキ役に変えることができるとする研究成果についての論文を2003年に発表した。「この研究が決定打となり、制御性T細胞が免疫学者の中で『市民権』を得た」(堀教授)という。
長年懐疑の目にさらされた研究は、今や医療応用へと道を開きつつあり、自己免疫疾患や臓器移植、がんなど広範な領域に拡大。がん免疫療法では臨床研究も進んでいる。堀教授は「ともに研究を推進した立場として、その意義がノーベル賞として評価され、大変うれしく誇りに思う」と喜んだ。
今後については「制御性T細胞がどのような仕組みで免疫を抑制しているのか解き明かすことが自分の研究課題だ」と語った。
【時事通信社】
〔写真説明〕坂口志文・大阪大特任教授の文化勲章受章を祝う祝賀会で、坂口夫妻と並ぶ東京大の堀昌平教授(左)=2020年2月、大阪市(本人提供)
2025年10月11日 14時32分